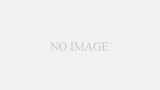テレワーク
テレワークを導入している企業が増えています。しかし、いざテレワークを導入しようと思っても、そう簡単に導入できるものではありません。まずはテレワーク導入の注意点を確認しておきましょう。この記事は、厚生労働省の「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」などを参考にまとめています。
労働時間の管理が困難
労働時間の管理の難しさは多くの企業が頭を悩ませているところです。理由は、仕事とプライベートの時間の区別が困難であったり、就業開始時間や終了時間があいまいになったりするからです。特に小さなお子さんがいるご家庭などでは、仕事時間中にやむをえず子どもの世話をすることになったりもするため、時間を管理する側としては悩むことになります。
情報セキュリティ対策が難しい
2つ目の注意点は、情報セキュリティ対策です。特に、従業員に会社専用のモバイルPCを用意できない企業は悩みの種になります。なぜなら、従業員の個人PCは家族で共有している場合もありますし、セキュリティ面において万全ではないからです。さらに、家だけでなく周りに人がいるカフェなどで作業する場合もあるため、個人情報を守る対策が必要になります。
評価が困難
注意点の3つ目は、評価が難しいことです。従業員の労働状況を管理できないため、評価が困難になります。また、従業員側も評価を正当に行ってもらえるか不安に思っており、評価基準があいまいだと問題が大きくなる場合があるので注意が必要です。
コミュニケーションが取りづらい
4つ目の注意点は、コミュニケーション面で問題が発生することです。日ごろからChatworkやSlackなどのチャットツールを活用していれば問題ないかもしれませんが、そうでない場合は課題になります。対面でのコミュニケーションが多い企業だと、オンラインでの連絡に違和感を持つ人もおり、孤立感を深めるなど、人間関係にも影響を及ぼす場合があります。
長時間労働になりやすい
注意点の5つ目は、長時間労働になりやすいことです。1つ目の注意点である「労働時間の管理が困難」とかぶる問題でもあります。会社への出勤、退勤があるわけではないため、朝早くから作業したり、夜遅くまで作業したりする可能性が生じます。評価に対する不安があるため必要以上に成果を出そうとする向きもあります。
その他
これまでに紹介した5つの注意点以外にも ・業務の進捗確認が難しい ・PCやシステム導入のコストがかかる ・安全衛生管理が困難 ・労働災害に該当するかの判断が難しい
など、たくさんの注意点があります。
デメリットを克服する対策については後述しますが、その前に公平性を期すためテレワークのメリットも確認しておきましょう。
テレワークには6つのメリットがある
テレワークはデメリットばかりではなく、当然数々のメリットもあります。導入する際、従業員と企業側の共有事項にもなるので確認しておきましょう。
通勤時間がなくなる
会社へ通勤する必要がないため、通勤時間を削減できます。その分、睡眠やプライベートに時間を回せるため、社員のコンディションや生産性が向上、テレワークのメリットの柱と言えます。
仕事が効率化され、生産性が上がる
テレワークは在宅や会社以外での場所での勤務となるため、仕事が効率化されます。総務省の2018年の調査によると、労働生産性向上目的でテレワークを導入した企業の内、80%以上が効果を多少なりとも感じています。
私生活が充実する
テレワークは通勤時間が無くなることや家で作業できることもあり、プライベートを充実させることができます。私生活が充実すると、ワークライフバランスが適切になり、結果として会社への貢献度が上がる可能性もあります。
離職率が減る
私生活が理由での離職率が減る可能性があります。例えば、介護や育児などです。本人も収入を得ながら、私生活への比重を増やせるので、会社を辞める理由がなくなります。企業側も辞められずに済みますし、こちらもテレワークのメリットと言えるでしょう。
採用の幅が広がる
テレワークであれば、通勤圏の人に限らず、広い範囲から人を採用することができます。母数が増える分、優秀な人が集まりやすくなります。
コストが減る
全社員を収容するオフィスを構える必要がなくなれば、固定費を削減することができます。オフィスコストを削減した分をテレワークの拡充に使うことで好循環にもつながります。
テレワークを成功につなげる7つのポイント
ここまではテレワークの注意点とメリットをまとめてきました。ここからは、テレワークを成功につなげる7つのポイントを紹介します。注意点やメリットを思い出しながら読んでみて下さい。
仮説と検証のサイクルを回す
まず、PDCAのサイクルを回すことが大前提になります。テレワークを導入しようとすると問題が山積みになるので、1つずつ仮説を立て、検証し、解決する、という流れをスピーディーに回すことです。最初から成功するとは思わず、ルールを変更しながら最適化していくことが大切です。
テレワーク導入の目的を共有する
なぜテレワークを導入するのかの認識を企業と従業員で共有しておきましょう。さらに、テレワークを導入することによるメリット、想定される問題点なども事前に共有しておくことです。共有した上で、定期的にテレワークへの満足度やルールについてアンケートを取ることもおすすめします。
労働時間を客観的に記録する
労働時間は客観的に管理することが重要です。例えば、タイムカードやICカード、PCの使用時間などがあります。労働時間の主観的な管理、つまり自己報告の場合、適切な時間管理は難しくなります。
また、労働時間中のプライベートな時間(中抜け時間)の取り扱いにも対策する必要があります。休憩時間とするか、時間単位の年次有給休暇とするかなど、企業と従業員で共有しておきましょう。
情報セキュリティ対策をする
情報セキュリティ対策として、まずはPCを従業員以外に共有できないものにしましょう。従業員が家族と共有して使っているPCや従業員がプライベートで使っているPCとは別にすることが一番です。 また、オンライン会議は原則自宅で行うようにした方がいいです。コワーキングスペースなどの人がいる環境ではいつ重要な情報を言ってしまうか分かりません。
さらに、公共の無料Wi-Fiを使わないことやのぞき見防止フィルムを張ることなど徹底的に対策しましょう。
長時間労働への具体的対策を行う
長時間労働対策として、喫緊の連絡以外、労働時間外にメールやチャットを送らないことです。メッセージが来るとどうしても気になり、作業してしまうかもしれません。業務時間外のやり取りは控えるようにしましょう。
また、社内システムを労働時間外に使用不可にすることも対策の一つです。もちろん、使用不可にすることによるデメリットもありますので慎重な判断が必要です。
最後に、長時間労働した社員への注意喚起を行いましょう。もちろん、決められた時間外の労働を禁止することは当然ですが、それでも働いてしまう人はいますので管理が必要です。
評価を明瞭にする
社員の評価方法を明確にしましょう。企業側だけが分かっていても、従業員側は正当に評価してもらえるか不安なので、誰でもわかるように評価を透明にする必要があります。企業からすれば労働状況が分からず正当に評価しているつもりでも、従業員からすると不当に評価されていると感じる場合があるかもしれません。評価を明確にして共有することで対策しましょう。
資料をペーパーレス化する
紙の資料は0にしましょう。どこからでもアクセスできるようにしておくことが一番です。ペーパーレス化することで生産性も上がります。社内専用のクラウドなどを用意し、ネットがあればアクセスできる状況にしておくことをおすすめします。
テレワーク導入企業からやり方を学ぶ
ここではテレワークをすでに導入している企業を6社紹介します。具体的な施策が分かるようにURL等も載せていますのでご参照ください。
レノボ・ジャパン合同会社(テレワークスタートガイド無料配布)
レノボ・ジャパン合同会社は、テレワークのスタートガイドを無料配布しています。 レノボ・ジャパン合同会社のテレワークスタートガイドでは ・テレワークについて ・テレワークの導入 ・テレワークの実施・定着 ・対応マニュアル の4つの章で構成されています。
レノボ・ジャパン合同会社は2015年からテレワークを制度化している企業であるため、とても参考になるはずです。ぜひご一読を。
参照:始めよう! テレワークスタートガイド
大同生命保険株式会社(厚生労働大臣賞優秀賞)
次に「令和元年度テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の優秀賞を獲得した大同生命保険会社を紹介します。
輝くテレワーク賞の優秀賞は毎年1社しか選ばれず、テレワークの取り組みが特に優秀な企業に贈られるものです。大同生命保険会社が簡単にまとめたテレワークの取り組みでは、導入から定着までの簡単な道のりや導入のポイントが簡単にまとめてあります。
参照:大同生命保険のテレワークと働き方の刷新
まとめ
今回は、テレワークの注意点とメリット、成功につなげるポイント、実践している企業をまとめました。テレワークを導入するには様々気をつける点がありますが、定着すればメリットが大きいです。今回の記事を参考にしてもらえたらと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。