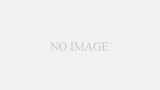パソコン
Windowsのパソコンを長く使っていると、急に起動しなくなることがあります。パソコンが起動しなくなる原因はさまざまあるので、どのような対処を行えば良いか押さえておくのが大切です。今回は、Windowsのパソコンが起動しなくなったときの対処法を紹介します。
パソコンが起動しないときにまず試したいこと
まず始めに、Windowsのパソコンが起動しない原因は無数にあります。そのため、なるべく自分で原因を突き止められるようにすることが大切です。最悪のケースだと修理に出すか、買い替える必要があります。
いずれの場合でも、パソコン内のデータが消えたり、仕事などでパソコンを操作できなくなったりなど、さまざまな影響が出るので注意しましょう。まずは、Windowsのパソコンが起動しないとき、最初に確認したいことを紹介します。
パソコン本体の電源周辺を確認する
パソコン自体が起動しない場合、電源周辺に異常があることが多いです。例えば、パソコン本体のプラグがコンセントから抜けていることは少なくありません。
他にも電源の接続が甘いなど、本体の不具合が起きていることで電源が入らず起動しないこともあるので、まずは電源類を確認しましょう。意外と電源類を見直すだけで、パソコンが起動するケースは多いです。
また、本体から電源を抜いてみるのもおすすめです。デスクトップパソコンの場合は、電源アダプターを本体から外し、ノートパソコンの場合はバッテリーを外します。この作業は「放電作業」というもので、パソコン内部の電気を放出することです。長期間パソコンを使っていると、本体の内部に電気が溜まり(帯電)、電源関連に異常が起きることがあります。パソコン電源周辺の確認をするのと同時に、放電も行うと良いでしょう。
他にも連続して使い続けていたり、冷却ファンにホコリが溜まるなどして動きが悪くなっていたりすると、パソコン本体が熱を持ち電源に異常が出ることもあります。特に長く使っているとファンにホコリが溜まってパソコンが熱くなるので、ファンを掃除することも大切です。
モニターを確認する
デスクトップパソコンの場合、パソコン本体に異常はなくても、モニターに不具合が起きていれば、画面が真っ暗な状態になってしまいます。この場合、パソコンの本体は起動していても、画面には何も映らない状態になっています。
モニターの電源が入っていなかったり、パソコン本体と繋ぐケーブルが外れているケースが考えられます。パソコン本体は動いているのに、画面がつかない・暗いままである場合は、モニター周辺を疑いましょう。
パソコン本体が起動していないときの対策
パソコン本体が起動していない場合、電源周辺をチェックしても異常がないときは本体が故障している可能性がかなり高くなります。放電をしても電源がつかない場合、ほとんどの人では手出しできない状況といえます。
パソコンに詳しく、本体を開いてみて原因が分かる方以外は起動させることが困難です。この場合は、修理に出すか買い替えなければなりません。
パソコン本体は起動しているときの対策
パソコン本体は起動しているのに、画面が同じ状態で変わらなかったり、すぐに暗くなってしまったりすることがあります。この場合は、いくつかの方法を試すことで改善されることもあります。では、パソコン本体は起動しているのに、Windowsが起動しない場合の対策を見ていきましょう。
再起動する
まず最初に試したいことが再起動です。原因が不明な場合、再起動をすることで回復することがあります。パソコン本体の電源を長押しして、強制的に電源を落としてもう一度起動してみます。上手く起動できていなかった場合、正常に終了できていなかった場合などは、再起動することで症状が回復することがあります。
セーフモードで起動する
前回の電源を切る前に、ドライバーやアプリ、システムなどをインストールした場合や、新しい機器を接続した場合など、何かパソコンの環境を変えたときは、それが原因で起動しないケースもあります。
この場合は、原因となっている要因をアンインストールしたり、取り外したりすることで回復する可能性が高いです。ただし、Windowsが起動せず操作ができないと環境を元に戻すことはできません。
そこで、試してみるのが「セーフモード」です。セーフモードとは、必要最小限のシステム環境でパソコンを起動するWindows診断用モードです。
Windows10の場合は、起動が高速なのでWindowsボタンと「Rボタン」を押し、「ファイル名を指定して実行」を立ち上げ、「msconfig」と入力します。次に「ブート」を選択し、「セーフブート」にチェックをして、任意の起動方法を選択してOKを押します。
その後、手順に沿うと「システム構成」という画面が出たら、再起動して完了です。このセーフモードで起動し、直近で追加した環境を元に戻しましょう。
Windowsの自動修復オプションを利用する
セーフモードで起動するか、強制再起動を2回以上をすると「自動修復」が始まります。この自動修復が始まるとパソコンが診断され、修復されます。ただし、必ず修復されるわけではないので注意してください。
初期化する
最後の手段ですが、自動修復中にはパソコンを初期化することが可能です。初期化をすると、追加したアプリやWindowsの設定などは全て削除されます。ファイルやアカウント情報は残すこともできますが、完全に削除することも可能です。
この初期化はWindows10の初期状態に戻す作業であるため、Windows自体に問題が合った場合に回復できる可能性があります。
最悪の事態に備えることも大切
パソコンの不具合の要因はさまざまあり、前日まで問題なく使えていても急に使えなくなることもあります。急にパソコンに不具合が出てWindowsが起動できなくなると、仕事などに影響するので、最悪の事態に備えることも大切です。ここからは、最悪の事態に備える方法を紹介します。
バックアップを小まめに取る
基本的な対策は、仕事などで使うデータはパソコン本体以外の場所にバックアップを作成して保管することです。自動でバックアップできる仕組みを構築すれば、作業の負担なくデータを保存できます。
パソコンに異常が出る直前までのデータを保存していれば、パソコンが起動しなくなりデータが取り出せない状態になっても、失われるデータの量を少なくできるでしょう。ただし、データが残っていても、普段使っているシステムやアプリなどが使えないと意味がないケースもあるので、バックアップのデータを復旧して使える体制を整えることも大切です。
クラウドのアプリ・システムを利用する
仕事などで使っているシステムやデータなどをパソコンのローカル上で管理していると、パソコンに異常が出たときに使えなくなってしまいます。そこで、クラウドのアプリやシステムを普段から使っていれば、今使っているパソコンが起動しなくなっても、他のパソコンを使って作業できます。
もし、全ての作業をクラウド上で行っており、パソコンのローカル上にほとんどデータを保存していない状態であれば、新しいパソコンを用意するだけで今までとほとんど同じ状態でパソコンを使えるようになります。
例えば、Googleのアプリであれば、メールはGmail、Excelはスプレッドシート、Wordはドキュメントといったものが使えます。Googleのアカウントを持っている個人・企業は多く、各ファイルは自動で保存されるのでバックアップ性も高いので便利です。
まとめ
パソコンはさまざまな原因で故障し起動しなくなります。パソコンの各パーツが老朽化していることで動かなくなることもあります。他にも、さまざまな処理を一度に行うとパソコンが固まってしまい、再起動しても動かなくなることもあるでしょう。
パソコンを長持ちさせたい場合は、なるべく処理の負担が大きくならないように気をつけることが大切です。例えば、小まめにアップデートし最新版にすることと、使わないデータは削除して容量を確保するようにしましょう。
Windowsのパソコンが起動しなくなる原因や対処法を把握することも大切です、万が一の事態になったときの対策も大切です。万全の対策を行って、パソコンに異常が出た場合にも対処できるようにしましょう。